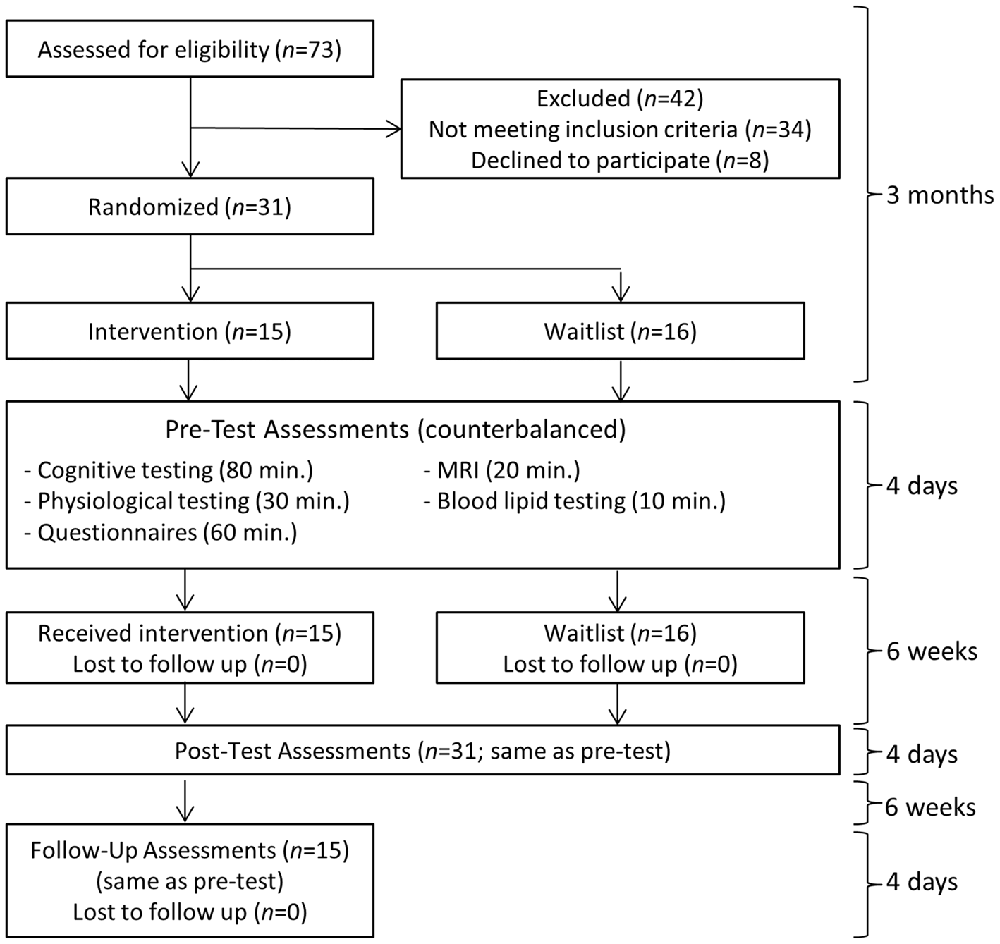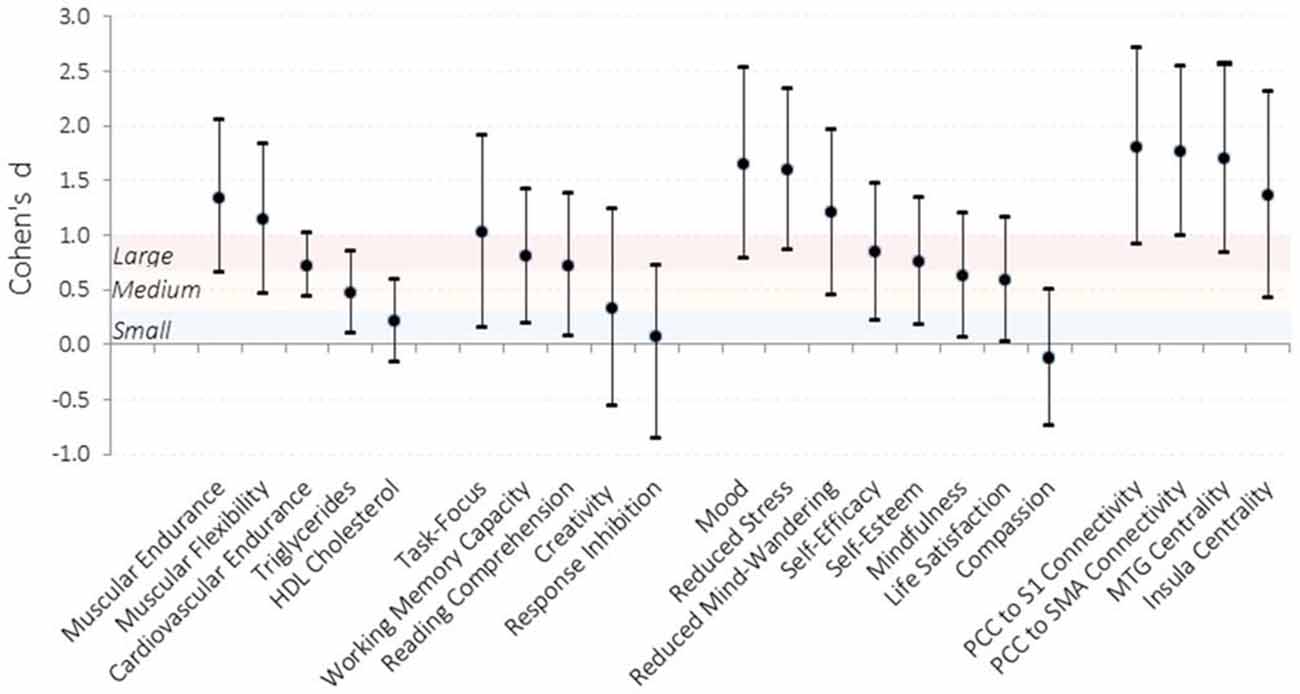皆さんは「カリフォルニア大学式人生改造プログラム」というものを聞いたことはあるでしょうか?
パレオさんこと鈴木祐さんや、メンタリストDaiGoさんが紹介していることでも有名なのでご存知の方も多いと思います。(以下にリンクを貼っておきます👇)
この記事ではその「カリフォルニア大学式人生改造プログラム」について取り上げ、プログラムの概要や実験方法、実験結果、評価スケールなどについて徹底解剖していきます。
カリフォルニア大学式人生改造プログラムの元ネタは?
このプログラムは「カリフォルニア大学式」とある通り、2016年にカリフォルニア大学のサンタバーバラ校で行われた実験です。(実験の詳細は以下のリンクからご覧いただけます👇)
(邦訳)「限界の押し上げ:集中的かつ多面的な介入によって明らかにされた認知的、感情的、および神経の可塑性」
このタイトルを見ると、元々人々の人生を改善するプログラムを作るという目的で行われたものではなく、人間の主に認知および心的機能の底上げを期待して行われた実験のようです。
2000年代までは、「人間の脳は新しい神経細胞は作れない」「人間の幸福度は変わらない」「ワーキングメモリーは変わらない」といったふうに、人間の能力の可塑性に対して否定的な研究がいくつかありました。
ただこの実験の研究者は、最近ではそれが疑問視され始め、運動や食事管理、瞑想、睡眠などによって人間の能力の限界値を底上げできる可能性があると主張しています。
またこれらの介入行動を単体で行うよりも、複数を組み合わせて行う方が効果が高いのではないかという仮説も立ちました。
さらに、身体的機能の向上と認知及び心的機能の向上はそれぞれ独立しているものではなく、相互に影響し合っているとも考えました。
そうした経緯もあって、運動や食事、睡眠、メンタルトレーニングといった、複数の介入行動がどれほど人のあらゆる機能に影響を与えるかを測るためにこの実験は行われました。

実験方法
以下の画像は実験の流れを図式化したものです👇
実験の概要
この実験の概要をまとめると以下の通りです👇
- 31名の実験参加者をプログラム実践者(15人)と待機グループ(16人)に振り分ける
- 実験参加者31名に対してプログラム事前評価の実施(4日間)
・認知機能テスト(80分)
・身体機能テスト(30分)
・アンケート(60分)
・MRI検査(20分)
・血液・脂質状態検査(10分) - 15人がプログラムを実践し、他の16人は待機(6週間)
- 実験参加者31名に対してプログラム事後評価の実施(4日間)
→事前評価と同様 - 普段の生活に戻ってもらい、一定期間経過させる(6週間)
- フォローアップ評価の実施(4日間)
プログラム内容

実際に行われたプログラムで行った内容は「運動」「食事」「睡眠」「メンタル」の4つのカテゴリーに分類できます。
それぞれのカテゴリーにおいて、どんなことを行ったか見ていきましょう。
運動
朝起きたら1時間のストレッチ
プログラム期間中は毎朝1時間のストレッチから始まります。
ストレッチをすることで体の柔軟性やバランス感覚、身体認識能力などの向上が期待できます。
実験では1分あたり5回の呼吸と、普段よりも深い呼吸が出来るような音楽が流されています。
深い呼吸の重要性についてはこちらの記事で解説しております👇
身体機能を高める運動
実験では以下のような内容と頻度で実施されました👇
- ピラティス(週2、1時間半)
- ヨガ(週1、1時間半)
- 自重サーキットトレーニング(週1、1時間半)
- HIIT(週2、時間指定なし)
食事
食事に関しての決め事は以下の3つです👇
- アルコールは飲むとしても1日1杯に留める
- 加工食品は一切摂らない
- 炭水化物の摂取は運動後に制限する
※①の目安 蒸留酒:約40ml ビール:約340ml ワイン:140ml
睡眠
睡眠に関しては、「毎晩8〜10時間の睡眠を取る」という決まりのみです。
10時間は流石に寝過ぎかなという印象を受けますが、日本人には「普段5,6時間しか寝ない」という方も多いと思うので、7~8時間くらいの睡眠時間は確保しておきたいところです。
睡眠の重要性についてはこちらの記事で解説しております👇
メンタル
1時間のマインドフルネス訓練
実験では以下の3つのバリエーションで行われたようです👇
- 呼吸に集中する瞑想
- 歩行瞑想
- 慈悲の瞑想
1時間半の座学
参加者は体を動かしたりするだけでなく、毎日1時間半使って以下の内容についての知識を学べる講座やディスカッション、アクティビティに取り組みました。
- 運動・栄養・食事
- アルコール消費
- マインドフルネス・注意力
- 感謝の心・共感性・思いやり
- 積極的傾聴
- ストレス管理
- 目標の追求
- 幸福・ウェルビーイング
1日1回親切な行いをする
これは文字通り他者に親切な行いをします。
親切な行いをすることで「幸福感の高まり」「心理的余裕の獲得」といった効果が期待できます。
また、この親切な行いは「あのときの行動は親切な行いだったな」と思い出すよりも、意識的に親切な行いをする方が効果が高まることがわかっています。
幸福感の重要性についてはこちらの記事で解説しております👇
実験結果
実験結果を視覚的に分かりやすく示した画像がこちらです👇
プログラム実践者と待機グループの効果量の差
この画像の縦軸の「Cohen’s d」は統計用語で、「群間差についての効果量であるd族の一つで、平均値の差を標本標準偏差で割って標準化したもの」だそうです。

細かいことはよく分かりませんが(笑)、「値が高ければ高いほどプログラム実践の効果が出ている」ということなのは分かります。
また、画像の中で「Large」「Medium」「Small」とあるので、それぞれの領域に値がある場合、「効果:大」「効果:中」「効果:小」と判断するということが分かります。
それでは実験結果の詳細について「身体機能」「認知機能」「心的機能」「脳機能」の4つに分けて見ていきましょう。
身体機能
「身体機能」については以下の項目の効果を測定しました👇
- Muscular Endurance:筋持久力 → 超効果ある
- Muscular Flexibility:柔軟性 → 超効果ある
- Cardiovascular Endurance:心肺持久力 → 効果:大
- Triglyceride:トリグリセライド(中性脂肪) → 効果:中
- HDL cholesterol:HDLコレステロール → 効果:小
身体機能の項目については「筋持久力」と「柔軟性」に特に効果が高いことがわかりました。
この効果のおかげで身体が疲れにくくなったり、怪我の発生の可能性を減らすことができます。
認知機能
「認知機能」については以下の項目の効果を測定しました👇
- Task Focus:タスクフォーカス → 超効果ある
- Working memory capacity:ワーキングメモリー → 効果:大
- Reading comprehension:読解力 → 効果:大
- Creativity:創造性 → 効果:中
- Response inhibition:反応性抑制 → 効果:小
認知機能に関しては「タスクフォーカス」、つまり「集中力」の向上にとても効果があることがわかりました。
心的機能
「心的機能」については以下の項目の効果を測定しました👇
- Mood:気分 → 超効果ある
- Stress:ストレス → 超効果ある
- Reduced Mind Wandering:注意力 → 超効果ある
- Self-Efficacy:自己効力感 → 効果:大
- Self-Esteem:自尊心 → 効果:大
- Mindfulness:マインドフルネス → 効果:中
- Life Satisfaction:人生満足度 → 効果:中
- Compassion:思いやり → 効果:小
「心的機能」に関しては「気分」「ストレス」「注意力」の3つの項目に関して特に効果があることがわかりました。
普段ストレスを感じやすい人だったり、鬱傾向が高い人にとってはめちゃくちゃ効果的のようです。
脳機能
「脳機能」については以下の項目の効果を測定しました👇
- PCC(Posterior Cingulate Cortex)to S1(somatosensory cortex)Connectivity:後帯状皮質と体性感覚皮質 → 超効果ある
- PCC(Posterior Cingulate Cortex)to SMA(supplemental motor area)Connectivity:後帯状皮質と補足運動野 → 超効果ある
- MTG(Middle Temporal Gyrus)Centrality:中側頭回 → 超効果ある
- Insula Centrality:島皮質 → 超効果ある
これらの効果はMRI測定によって判明したものです。
正直自分には何がどう効果があるのかさっぱりわかりませんが(笑)、とにかく脳機能の向上にすごい効果があったようです。
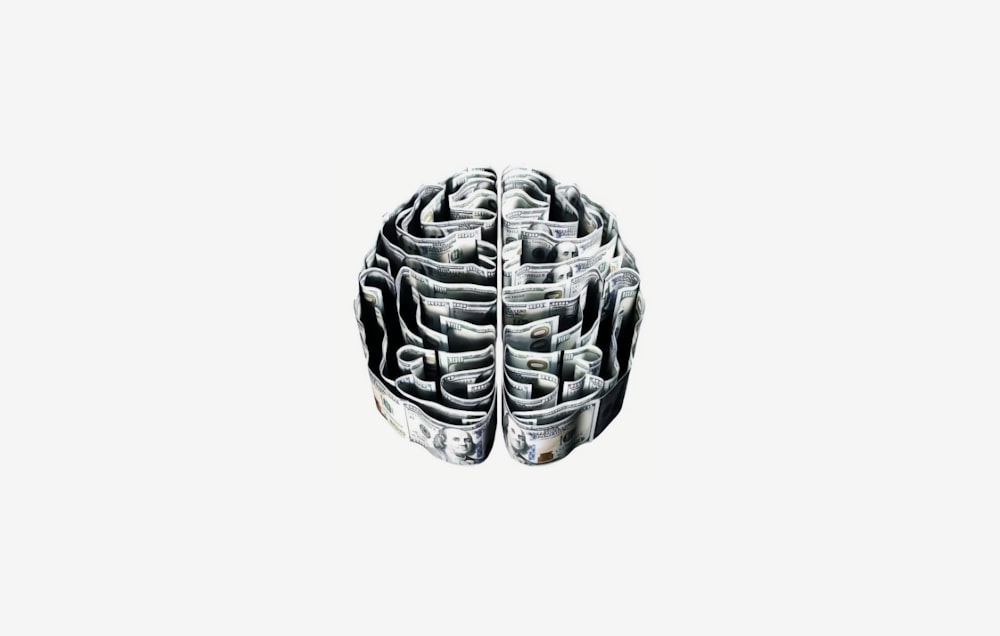
評価方法
また、この実験で使用された各機能における評価方法および評価スケールを記載するので、自分の健康状態を測定したいという方は参考にしてみてください♪
身体機能
身体機能に関してはそれぞれの項目において評価方法があり、以下がその一覧となります👇
評価方法一覧
- Muscular Endurance:筋持久力 → Sport-specific endurance plank test
- Muscular Flexibility:柔軟性 → Back-Saver Sit & Reach Test(日本語版はこちら)
- Cardiovascular Endurance:心肺持久力 → Incremental max velocity treadmill test
認知機能
認知機能に関してもそれぞれの項目において評価方法があり、以下がその一覧となります👇
評価方法一覧
- Task Focus:タスクフォーカス → Sustained Attention to Response Task (SART)(この実験では使用されていませんが注意力を測定する上で有効なテストです。結構楽しいですよ笑)
- Working memory capacity:ワーキングメモリー → Operation Span Task (OSPAN)(16分間のデモ版が体験できます)
- Reading comprehension:読解力 → Graduate Record Examination (GRE)(この実験ではボキャブラリーテストパートを省いています)
- Creativity:創造性 → Remote Associates Test(日本語版の論文はこちら)
- Response inhibition:反応性抑制 → Attention Network Task(20分間のデモ版が体験できます)
心的機能
心的機能に関してはそれぞれの項目においてアンケート形式の評価項目が使用されており、以下がその一覧となります👇
評価スケール一覧
- Mood:気分 → Positive and Negative Affect Schedule
- Stress:ストレス → 4-item Perceived Stress Scale
- Reduced Mind Wandering:注意力 → 5-item Mind-Wandering Questionnaire
- Self-Efficacy:自己効力感 → New General Self-Efficacy Scale
- Self-Esteem:自尊心 → 10-item Rosenberg Self-Esteem Scale
- Mindfulness:マインドフルネス → Mindful Attention and Awareness Scale
- Life Satisfaction:人生満足度 → 5-item Satisfaction with Life Scale
- Compassion:思いやり → 5-item sub-scale of the Positive Emotion Dispositions Scale


まとめ
今まで見てきたように、このプログラムを実践すれば私たちの心理的および生理学的機能など、あらゆる機能の向上が期待できることが分かりました。
また、先ほど実験結果の画像としてお見せした通り、「ストレスの解消」と「気分の改善」に対してはものすごく効果があることがわかり、なんとメンタルトレーニング単体を実施する場合と比べて2.5倍もの効果があるみたいです。
さらにすごいことに、プログラム終了から6週間経った後のフォローアップ評価によると、トレーニングで得た効果が6週間後も持続していたというから驚きです。
さすがに何年経っても永続的に効果が持続するとは考えにくいですが、一定期間集中的にトレーニングに取り組むことで、最低でもトレーニング期間と同程度の期間で継続してトレーニングの恩恵を享受できると言えるでしょう。
そして僕自身このプログラムをやってみたくなったので実践してみることにします!
最後までちゃんとやり切れるか不安ですが、取り組んでみた感想や効果などを今後の記事でシェアできればと思っています!
それではまた〜♪
【追記(2021/1/1)】
実践後の変化を知りたい方はこちらの記事をご覧ください👇
最後まで読んでくださった方へのお知らせ
現在、健康に関する悩みの無料相談を行なっています^ ^
健康に関する悩みやご相談であれば何でも構いませんので、以下の公式ラインよりお問い合わせください👇